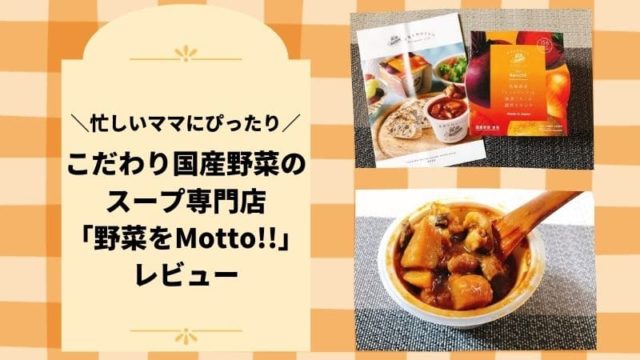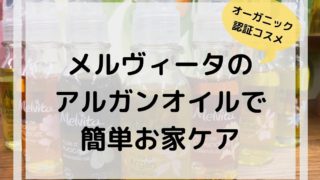まもなく始まる来年度の保育園の入園申し込みに、ドキドキしますね。
少子化という割には減らない待機児童。「認可保育園に入れなかったらどうしよう」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。
希望している認可保育園に入れたら一番良いですよね。
ですが、もしも認可保育園がダメだった時の選択肢として、小規模保育園や企業主導型保育園や認可外保育園という選択肢もあります。
横浜市には認可ではないけれど、多少の助成を受けられる横浜保育室という認証保育園もあります。
今日は、小規模保育園、企業主導型保育園、認可保育園全てを経験した我が家の体験談を含めて、それぞれのメリットやデメリットについてまとめていきます。
保育園の申し込みの際や万が一認可保育園がダメだった時の参考になると嬉しいです。
目次
認可保育園、小規模保育園と企業主導型保育園の全てを経験した我が家の状況

先に我が家の状況から書いて行きます。
長男は0歳クラス(8か月)から保育園に通っています。
1次で認可保育園に落ち、2次で小規模保育園に入園が決定。
2歳クラスで小規模保育園卒業後に、3歳児クラス(年少)から認可保育園に通っています。
次男は1歳クラス(1歳5か月)で申し込み。
1次も2次も認可保育園に落ちてしまいました。1次も2次もダメだった時の年度限定保育というのもありましたが、料金があまりかわらない企業主導型保育園に入園。
1か月経って慣れてきた頃に、長男が通っている保育園とは別の認可保育園に空きが出て、転園し現在は認可保育園に通っています。
4月の申し込みで次男を長男の保育園に転園させようか迷っている最中です。
長男は小規模保育園に3年間、次男は1か月だけ企業主導型保育園に通っていましたが、認可保育園と比べて不便な点は特にありませんでした。
認可保育園、小規模保育園、企業主導型保育園の申し込み先と引き落としについて

それぞれの保育園を希望する場合の申し込み先や引き落とし先はどこになるのでしょうか?
| 保育園種別 | 申し込み先 | 引き落とし |
| 認可保育園 | 市区町村 | 市区町村 |
| 小規模保育園 | 市区町村 | 運営企業 |
| 企業主導型保育園 | 運営企業 | 運営企業 |
※横浜保育室と認可外保育園は企業主導型保育園と同様です。
認可保育園は市区町村との契約になるので、引き落としは市区町村から引き落とされます。
小規模保育園は申し込みは市区町村で行いますが、運営企業との契約になるので引き落としは運営企業になります。
企業主導型保育園、横浜保育室、認可外保育園は企業との契約になるので、運営企業に申し込みをして、引き落としも運営企業です。
次男が通った企業主導型保育園は引き落としではなく、請求書を渡されて、振り込む仕組みでした。
企業主導型保育園、小規模保育園のメリットとデメリット
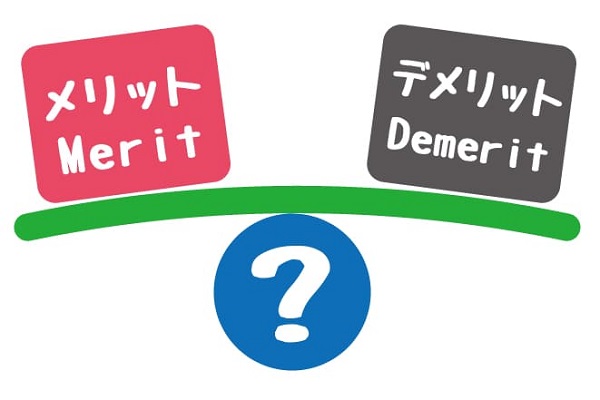
企業主導型保育園、小規模保育園に通って感じたメリットとデメリットを下記の順番でまとめてみようと思います。
- 企業主導型保育園のメリットとデメリット
- 小規模保育園のメリットとデメリット
①企業主導型保育園のメリットとデメリット

企業主導型保育園は企業が運営している保育園です。運営している企業の社員を優先的に受け入れて、残りの枠で地域の子どもを預かってくれます。
月額料金も企業が決められるので「こんなに安くて良いの?!」という保育園と「こんなにかかるの?!」という保育園と差が激しいです。
メリット
- 比較的新しい保育園が多い
- 持ち物が少なく済む場合がある
- 時間の融通が利く保育園も
企業主導型保育という制度が始まったのが平成28年度と比較的最近で、今どんどん参入している企業が増えています。
少しずつ増えているので、新しい園が多く、オモチャも設備もとてもキレイな所がまだまだ多いです。
次男が通っていた企業主導型保育園は、月額費用が高い分、持ち物は汚れた服の替えだけでOK。
通園用のカバンも用意してくれて、オムツもおしりふきも食事のエプロンやお手拭きまで全て用意してくれたので、入園間際にバタバタせずに済みました。
企業の方針にもよりますが、それなりの値段を払わなければならないだけあって、持ち物に関してはとってもラクチンでした。
我が家の近くにある企業主導型保育園は、週7日の保育や夜間保育も料金設定がされていました。認可ではないので、時間の融通が利く場合は多いようです。
デメリット
- 情報を自分で探さないといけない
- 狭き門の場合もある
- 認可に比べて高い場合がほとんど
企業主導型保育園は認可保育園ではないので、市区町村の保育園一覧に載っていません。なので、自分でネットで調べる必要があります。
私の場合、最初に区役所で対応してくれた方は「わかりません」と言って教えてくれず、別の担当者が対応してくださった時に「こんな園ができるんですが知っていますか?」と教えてくれました。
区役所で教えてくれることもまれにありますが、ネットで「企業主導型保育園 ○○(地域名)」で調べるのがオススメです。
ふと子ども達と散歩をしている時に偶然発見した保育園もいくつかあったので、意外と、近くにあるかもしれません。
まだまだ認知がされていなくて、空きがある保育園もあれば、大手企業の保育園の場合は、社員の方だけでいっぱいで地域の受け入れ枠は少ない場合があります。
次男が行った保育園は逆に人数が少なくて手厚い保育をしていただけました♪
料金は最初にも書いた通り、ピンキリです。認可より高い場合がほとんどですが、稀に認可に行くより安く済む場合もあります。
次男が通った所はとても良い園だったので利用中の不便さは特に感じませんでした。が、運営している企業については念のためしっかり調べるのがオススメです。
②小規模保育園のメリットとデメリット

長男が3年間通った小規模保育園のメリットとデメリットは下記の点でした。
メリット
- 目が行き届いていそうで安心
- 別の学年のパパやママともコミュニケーションが取りやすい
- ルールは認可とほとんど変わらない
認可ではありませんが引き落とし先が企業なだけで、利用する側としては、認可園とほとんど変わりません。
なんなら、今通っている認可園よりルールに関しては厳しかったです。これは企業の方針によるので、説明は省かせていただきます。
また、小規模保育園は2歳クラスまでの小さい子ども達だけなので、施設自体も小さい場合がほとんどです。
長男が通っていた所も0歳から2歳まで大人が見渡せる範囲にいるので、「うちの子見えてないんじゃ…」という心配が一切ありませんでした。
他のクラスのパパやママとも自然と挨拶するようになったり、「大きくなったね~」と言ったり言われたり、自分の子以外の成長も嬉しく感じたりしました。
デメリット
- 認可への転園が不安
- お友達との別れが寂しい
一番大きなデメリットは3歳からの保育園への転園の不安。それ以外は、特にデメリットは感じませんでした。
最初に小規模保育園に申し込んだ時は「2歳までなら記憶にも残らないだろう…」と思ってあまり気にしていませんでした。
ですが、卒園する頃にはお友達の名前もお互いに呼び合ったりしていたので、「お友達とのお別れ」が少し寂しかったです。
寂しかった反面、3歳で卒園式の晴れ姿を見れたのは嬉しかったです。
長男の保育園の場合、卒園後の進路は認可保育園に行った子が半分、幼稚園に行った子が半分。
入園受け入れ人数が0や1で激戦区と呼ばれていたので、不安は大きかったですが、保育園を希望した子は全員転園でき、幼稚園にも全員入れました。
正直、転園後の保育園で最初アウェイ感を感じてしまったり、保育園の方針にも慣れるまで時間がかかり、子どもがなじめるのかも心配でした。
でもそんな心配をよそに、子どもはすぐにお友達を作って仲良くなれました。
企業主導型保育園や小規模保育園のデメリットはほとんどなし

この記事を作成するにあたり、改めてメリットやデメリットを振り返ってみましたが、やっぱりほとんどデメリットは感じませんでした。
もし幼稚園への転園等も視野にある場合は小規模保育園も候補に入れても良いかもしれません。
5歳までの認可保育園に最初から通えれば、お友達とずっと一緒に成長できるメリットはあります。
ですが、小規模保育園や企業主導型保育園からの転園でも、子どもはすぐになじめるので大丈夫です。
企業主導型保育園は検索する手間と料金の高さがありますが、少しずつ増えてきているので、意外と近所に見つかる場合もあるかもしれません。
企業主導型保育園は認可がダメだった場合にエントリーだけしておくと、少し気持ちに余裕ができます。
予約金が必要な場合もあるので、その点はご注意ください。
保活お疲れ様です。希望の保育園に入れることを願っています!
読んでいただき、ありがとうございました。